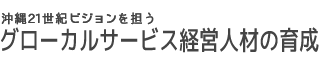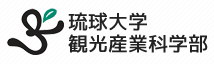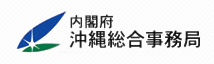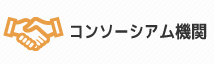【講義】5/25 第6回宿泊サービス概論
第6回 宿泊サービス概論 担当:平野典男
外部講師:株式会社光貴の皆様
第6回はブライダル施設見学で、株式会社光貴様のご協力により、北谷町にあるヴォヤージュ・ドゥ・ルミエール北谷リゾートを見学させていただきました。
ヴォヤージュ・ドゥ・ルミエール北谷リゾートは、海岸沿いに建っており、ブライズルームやチャペルなど全てがオーシャンビューだそうです。
まずはこだわりの施設を見学しました。チャペルには大きな窓があり、目の前に海が広がる設計になっていました。バージンロードをあえてモザイクタイルにし、波をイメージしているのだそうです。
主にリゾートウェディングが行われており、リゾートウェディングの概要について説明がありました。
・沖縄のリゾートウェディングは昨年15000組を超え、(10年前は6000組)
・インバウンドが1割を占めている
・リゾート婚の経済効果は、224億円
・インバウンドは、台湾、中国、韓国が多く、英語、中国語ができるスタッフが対応する
・ゲストの平均は、国内18.6人 海外22.9人
・海外のエキスポに参加し行政の協力のもと誘致活動を行っている
・最近はフォトウェディングが30%を占め、年々増加傾向にある
・カップルの希望に沿った式を演出する(ビーチでの挙式、サーフボードを結婚証明にする、レストランウェディングなど)
・トップシーズンは、10月、11月、4月、7月
・ボトムシーズンは、1月、8月、2月
・1月は年始ということ、8月は航空券の価格と台風の影響もありボトムシーズンとなっている
続いて、株式会社光貴様の事業概要について説明がありました。元々移動体通信事業からスタートし、ブライダルに参入。県内5社しかない上場企業に続き、現在上場を目指しているということです。また、人材育成にも力をいれており、その制度についてお話がありました。
次週は、株式会社光貴 取締役 西様をお招きし、講義を行っていただきます。









文責:観光産業科学部 宜志富知恵子
【講義】5/23 第6回サービスマネジメント論
第6回 サービスマネジメント論 担当:橋本俊作
外部講師:元ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 寺井太郎氏
第6回は、USJでマーケティングに携わっていた寺井太郎氏をお招きし、マーケティング戦略についてお話いただきました。
まずは、テーマパークの最新情勢として、日本の三大テーマパークの入場者数、料金、満足度について説明がありました。
テーマパークといえば、直接接客をしてくれるスタッフに目が行きがちですが、どういう部門があって、どういう業務をしているかお話いただきました。マーケティング部門では、アトラクションの企画、CMなどの屋台骨、オペレーション部門では、パークを安全、快適にする最前線、サポート部門は、会社の経営管理を行っているということが分かりました。
続いてメインのマーケティング戦略についてですが、新しいアトラクションを作るために、まず何をするかというマーケティング戦略のフレームワークについてお話がありました。まず、戦略目標をきめ、ターゲットを決め、届けたい価値を決め、中身を決めるという4つのステップがあるということでした。よく聞く、マーケティングの4P (product, price, place, promotion)というのは、最後の中身を決めるという段階の話なのだそうです。
とかく、何かを企画するときは、中身を決めてそこから価値、ターゲットなどを決めがちですがそれが逆の手順であるということが分かりました。確固たる目標を見据えた上での中身ということでした。
その上で、実際のCMを見て、ターゲット、届けたい価値が読み取れるか検証しました。
CMはターゲットにささればいいもので、「誰でも」という対象にしていると誰にもささらないのだそうです。
最後に顧客満足度を高めるためにどういう対応をしているかというお話があり、質疑応答の時間となりました。







文責:観光産業科学部 宜志富知恵子
【講義】5/22 第7回飲食ビジネス概論
第7回 飲食ビジネス概論 担当:上地恵龍
第7回は、飲食産業の原価管理および収益分析をとりあげました。
まず、ホテル施設では、シティホテル、リゾートホテル、宿泊特化ホテルなど、ホテルの種類によって、売上の内訳の割合が異なっていることについて説明がありました。
ホテルのレストランは、外食チェーンや、街のレストランとも競争しており、ホテルでしかできないスペシャルメニューやイベントで対抗しているそうです。その競争の中で、一つの選択肢として、飲食施設にテナントを導入するという方法もあり、その利点とリスクを学習しました。
これからの運営方法として、ホテルの飲食施設は、客数、料理の単価をあげること、固定人件費を活用しシェフの対面サービス強化、値ごろ感や余韻の演出などが必要になってくるということでした。
次に、売上原価とその計算方法について解説がありました。
原価管理のポイントとして、
①売上高の正しい把握:伝票の正確性、金銭授受の正確性、レジの正確性など
②振り替えのシステムの確立:試食や試作、接待分の正しい伝票処理
③ロス・ミスの処理:棚卸、破損、過剰スタンバイ、デッドストックの処理
④適正の在庫:品目ごとの標準在庫の確定
があり、原材料だけでなく、オペレーション中によい緊張感をもつこと、物を大切にすること、問題意識をもつことが大切だそうです。
続いて、ABC分析を教わりました。実際の表からどう読み取るかを考えました。売上がよくても原価率が高いものもあるので、一概に売上高の数字だけでは判断ができないこと、
売上実績からは、季節、価格弾力性、客単価コントロール、全体の伸び率などを読み取って分析をする必要があるということでした。
文責:観光産業科学部 宜志富知恵子
【講義】5/16 第5回サービスマネジメント論
第5回 サービスマネジメント論 担当:橋本俊作
第5回は「サービスをいかに収益化するか その2」でした。
第4回で行った「再利用回数を高める仕掛け」について、学生から上がった意見以外には、
・継続して利用しなければならない仕組み作り(囲い込み)
・SNSや口コミの促進
などもあるという紹介がありました。再利用という観点からみると、土産物店では、リピーターをあまり意識していないように見えるという特徴もありました。
Service-Profit Chainのまとめとして、Resource Based Viewの説明がありました。
企業が「持続的競争優位性」を保つためには「内部資源を活用する」ことが重要だそうで、それには、内部資源に価値がある、希少性がある、模倣が困難、最適な組織の条件を
満たす必要があるのだそうです。
Service-Profit Chainは最適な組織を表した図ともいえ、最適な組織を作り出す方策には、「インターナルマーケティング」があるということでした。インターナルマーケティングは、有能な従業員を彼らの欲求を満足させるような「仕事そのもの」によって引きつけ、育成し、動機付け、保持することで、従業員を顧客として扱う哲学であるという説明がありました。
続いて、リピーターの源泉である顧客ロイヤルティの重要性について解説があり、グループディスカッションとして、「地中海クラブ」について調べました。
地中海クラブは、顧客価値の高いサービス提供を維持し、顧客満足の高さを確保することで、リピート率をあげているそうで、リピーターがもたらす口コミは有効なマーケティングになっているということでした。
文責:観光産業科学部 宜志富知恵子
【講義】5/9 第4回サービスマネジメント論
第4回 サービスマネジメント論 担当:橋本俊作
第4回は「サービスをいかに収益化するか」というテーマでした。
「周りにある再利用回数を高める仕掛け(仕組み)を考える」というお題で、グループディスカッションを行いました。
学生からは、
・ステップアップクーポン(2回目は10%オフ、3回目はデザート無料など)
・ポイントカード
・店員が客を覚えていてくれる
・腕(技術)→美容院など
・サービスの追加(常連には一品サービス。あえてサービスするとは言わない)
・ゲームセンターでコインを預けられるというシステム
・品揃えを良くし、情報発信する(アパレルなど)
・店員さんが美人
という意見がでました。
続いて、Customer Journey Mappingと、Service-Profit Chainについて解説がありました。
Service-Profit Chainは、優れたサービスを生み出す仕組みを図式化したもので、ES、CS、利益の因果関係を示したフレームワークだそうで、その特徴について話し合いました。
学生からは、
・従業員の満足度が高いと顧客へのサービスの質が高くなる
・顧客が何を考えて購入するか、顧客の満足度などを従業員1人1人が理解をする必要がある という意見がでました。
文責:観光産業科学部 宜志富知恵子
【講義】5/1 第4回飲食ビジネス概論
第4回 飲食ビジネス概論 担当:上地恵龍
第4回は、「地域経済活性化に貢献する移動食」ということで、駅弁についてとりあげました。
まず「弁当」という文化が、近年海外でも人気になっており、アメリカ、フランスでのニュースを見ました。弁当はそのまま「BENTO」という単語になっており、本屋には弁当の料理本が売られていたり、弁当箱のコーナーもあるほど人気があるようです。
さて、駅弁ですが、学生に食べたことがあるか質問をしたところ、県外出身の学生は「食べたことがある」でしたが、沖縄出身の学生となるとほぼほぼおらず、内地に旅行に行ったときに食べたことがあるという学生が1名いただけでした。
そもそも、駅弁は、「駅」で売っている「弁当」なので、車社会沖縄には馴染みがないのですね。内地出身の私は、子供の頃、お土産にもらう駅弁にワクワクしたものです。デパートで駅弁フェアがあると、その地へ行った気になってつい買ってしまう魅力が駅弁にはあると思います。
駅弁の歴史は、元々は鉄道建設の作業員のための食事が起源のようで、それが乗降客にも提供されるようになり、地域の食材を使うことで、地域のブランド力向上や、地産地消に貢献するようになったということでした。
また、日本の「鉄道大国」という面や、弁当を持ち歩くことに抵抗がない気質、各地に特産品があるという地理的優位性が結びついてできた、日本独特の食文化になったそうです。
とはいえ、時代と共に市場は縮小しており、常温保存の駅弁は消費期限が短く廃棄率がコンビニなどの倍の10%あり、そこには、規制があって消費期限が近くなったものを値引きできないなどの理由もあるようです。また、鉄道の高速化による乗車時間の短縮、駅構内に整備される「駅ナカ」店の増加、コンビニの存在、固定窓式で開閉できない車両の増加などの理由もあり、老舗業者が撤退するということもあるということでした。
そこで、イベント出店や保温式・加熱式駅弁の開発などにより、駅弁による地域活性化を図る取り組みが行われるようになり、デパートで行われた全国の駅弁が一同に会する「駅弁大会」に出店する店の密着取材の様子を見ました。上位に選出されることで、全国区になったものもあるほど影響力があるのだそうです。
近年では、「駅」だけでなく「空弁」「球弁」「速弁」「道の駅弁」などもあり、各地域で工夫を凝らした弁当が販売されているということでした。
文責:観光産業科学部 宜志富知恵子
【講義】4/27 第3回宿泊サービス概論
第3回 宿泊サービス概論 担当:平野典男
第3回は宿泊部門の客室サービスについてでした。
予約からチェックアウトまでに、どういう職業の人が携わっているかと、宿泊部門を管理する側(マネジメント側)の業務について解説がありました。
利益の上げ方として、利益率が高い宿泊部門では、コストダウンより売上をあげたほうが利益がでやすいということでした。つまり、なるべく高い価格で満室状態にするのが売上につながり、レベニューマネジメントにより、販売量と価格を調整しているそうです。
ホテルだけでなく、航空機の予約などでもレベニューマネジメントは使われており、ユナイテッド航空で問題となったオーバーブッキングが起こる仕組みが分かりました。
次に宿泊部門の経営指標となる計算式についてとりあげました。
「販売可能客室1室あたり売上=RevPAR」を用いて表すそうで、平均客室単価(=ADR)×客室稼働率(=OCC)で求められるということでした。
平均客室単価、客室稼働率の出し方が分からないと出せないので、合わせて覚えましょう。
この講義は、サービス経営人材育成事業ですから、マネジメントに必要な数字を理解するのは不可欠です。ここは、ホテル業界でキャリアアップしていくためにも重要な項目ですので、専門用語も含め、計算できるように復習もしっかりとしておきましょう!
文責:観光産業科学部 宜志富知恵子