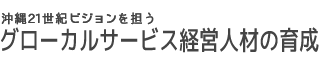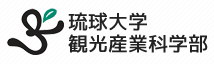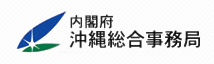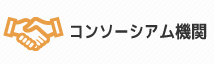【講義】11/30 第9回・10回MICEビジネス概論
2016.12.08
第9回 MICEビジネス概論 担当:下地芳郎
第10回外部講師:与那原町観光商工課 主事 宮平祥加氏
第9回は下地先生が、沖縄MICE振興戦略策定について取り上げました。なぜMICEが重要か、既存施設との役割分担、オペレーションの重要性(いかに顧客のニーズを先取りできるか)、ポジショニング(ライバルをどこに設定するか)などについて説明がありました。
その後、沖縄のMICEの競争力を増すための「ユニークベニュー」と、「その場所での魅力的なパーティー」の提案をテーマに、グループディスカッションとなりました。
1月の終わりにある講義でも、引き続きこのテーマでディスカッションをし、最終的には、提案書のプレゼンを行います。
第10回は、与那原町観光商工課主事 宮平祥加氏による、「与那原町の取組」についての講義でした。まずは、与那原町の基礎情報(面積、人口、学校、伝統、名物など)や、与那原町の観光の取組について、説明がありました。
大型MICE施設の受け入れに向け、与那原町が取り組んでいることとして、町民のMICEについての理解度の向上のための、町民対象MICE啓蒙セミナーの開催、地域にお金が落ちる仕組みを作るための観光協会の設立や、MICEで発生する仕事を、発地ではなく与那原町で受注するための組織構築、留学生の力を借りるといった国際的な人材の育成、与那原町の周辺地域との協力体制の構築などがあるということでした。
その後、
・アフターMICEを以下のジャンル別に考える
①チームビルディング、②エンターテイメント、③ケータリング、
④パーティー、⑤回遊プログラム、⑥記念品から3つ程度の提案をする。
・沖縄の東海岸っぽいイメージのメニューにする
という条件の元、グループディスカッションになりました。
学生からの提案は以下のようになりました。
①チームビルディング
・与那原町の名産品赤瓦を使い、チームごとにデザインを考え、赤瓦作りを体験する
・野菜収穫
・ウォークラリーをして温泉(猿人の湯)に行く
・朝ヨガ
・コースター作り
・MICE施設のヨットバースから出発するハーリーレースで結束力を強める
・ビオスの丘でサバイバルゲーム
・綱引き体験
②エンターテイメント
・朝ヨガや朝ウォーキング
・与那原水路での屋形船(2020年までに臭いなどの整備をする)
・キラキラビーチで朝ヨガ、ノルディック
・ひじき収穫
・釣り(ヨナバルマジクを養殖し、釣ったら食べられる)
③ケータリング
・タコライス発祥の地、金武町からキングタコス
・キロ弁を協力して食べ仲を深める
・沖縄っぽい弁当箱に東海岸の特産物を入れる
・牛車デザインの回転寿司
・与那原産ひじきのじゅーしー
・北中城のアーサースープ
・中城の島大根のおひたし
④パーティー
・うるま市の闘牛場を使用し、スクリーンで闘牛を見る。
・闘牛場でバーベキュー
・屋台村を作り沖縄料理の提供
・玉泉洞
・キラキラビーチでビーチパーティー
⑤回遊プログラム
・ビオスの丘で水牛車に乗る、体験型アクティビティ
・中城のパラグライダー
・コザの夜の街めぐり
・与那原の飲み屋めぐり(地酒があればそれを提供)
・脱出ゲーム
・パワースポットめぐり
⑥記念品
・チームビルディングでコンテストを行い、瓦のメダルを授与
・パワースポットにちなんだグッズ(パワーストーンなど)
・赤瓦コースター
・赤瓦で闘牛を作り、闘牛の匂いのアロマスティックにする
・サンライズを使ったポストカード、Tシャツ

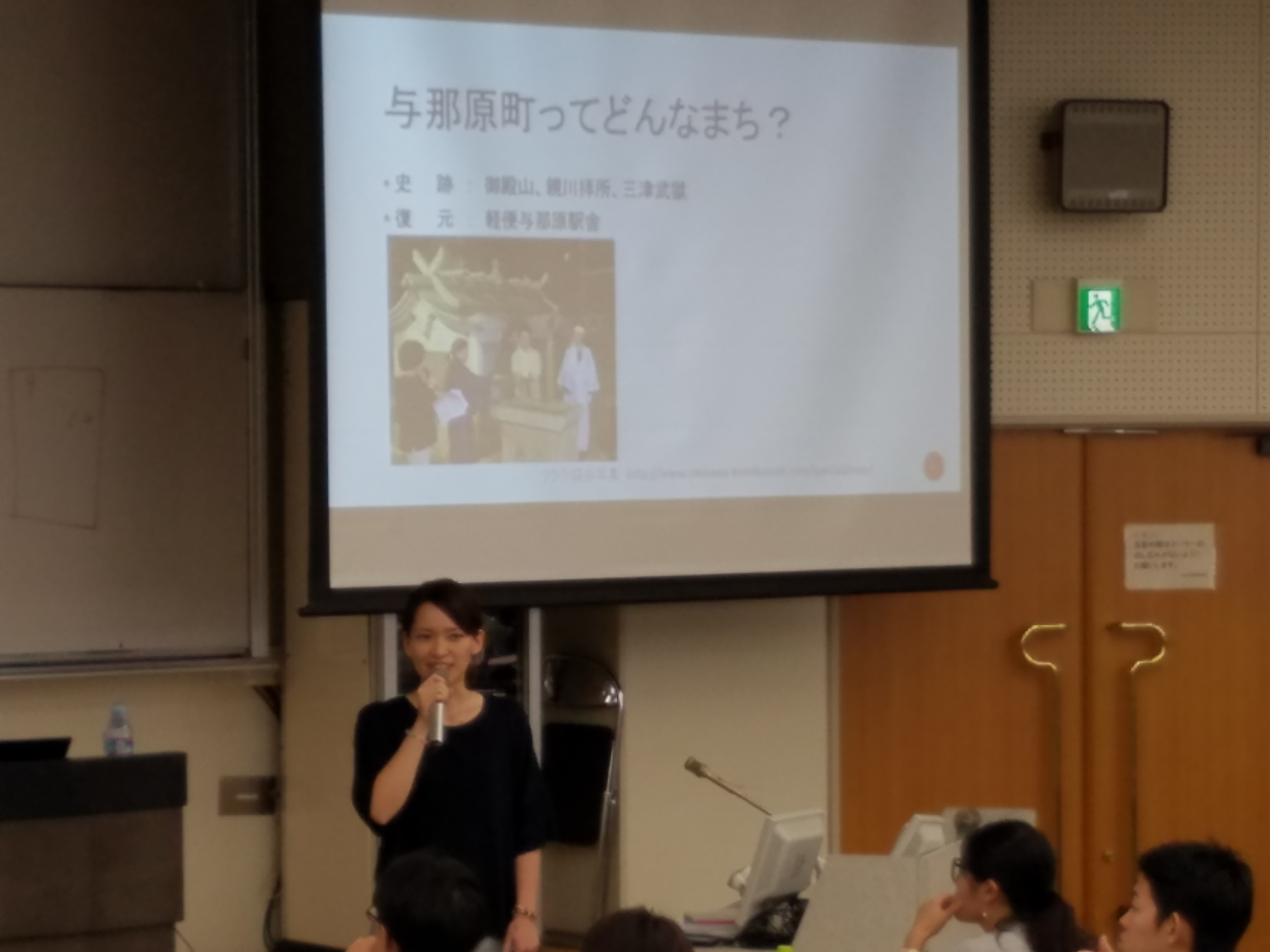


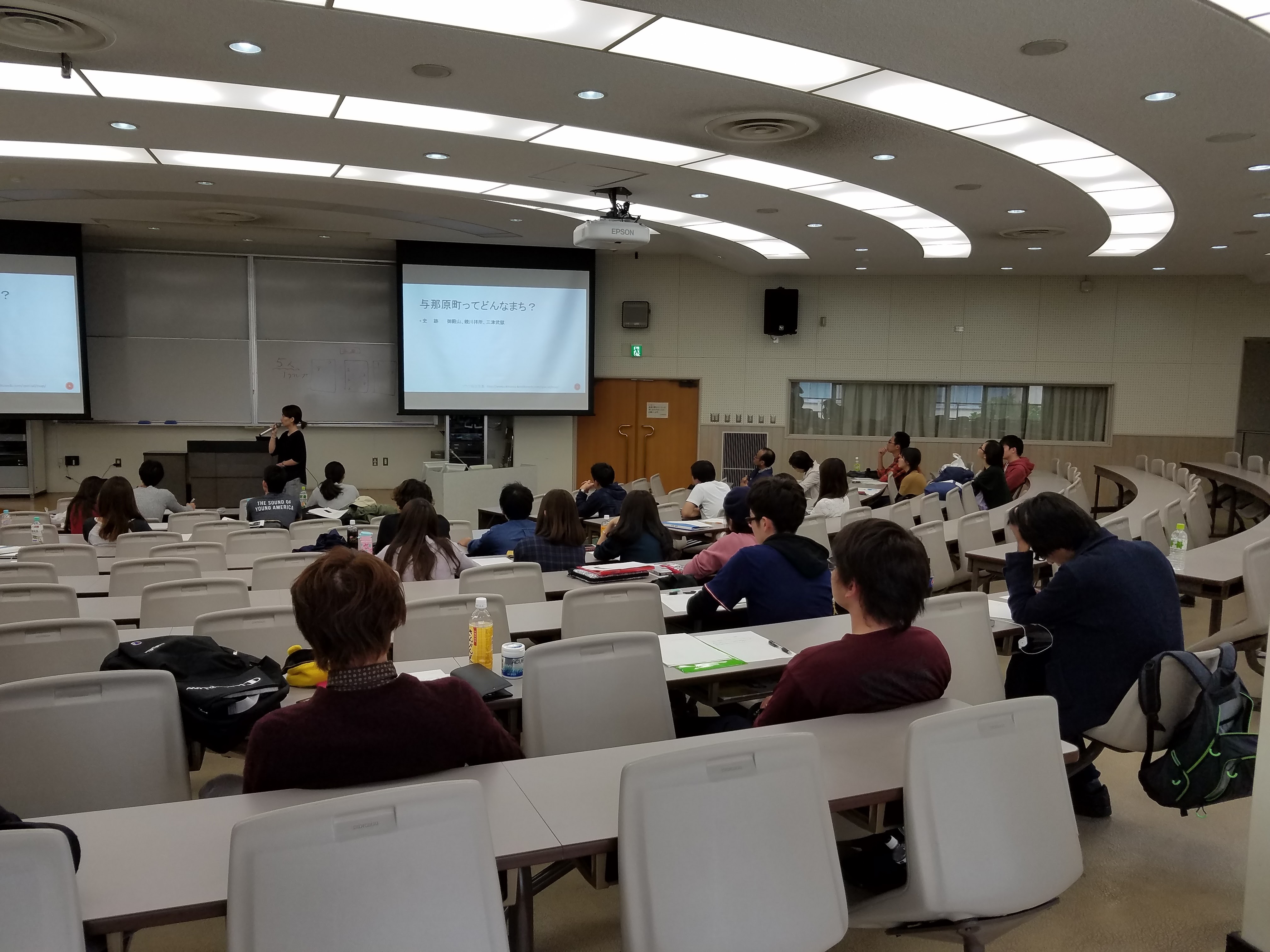
文責:観光産業科学部 宜志富知恵子