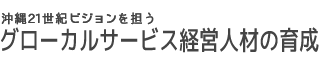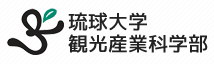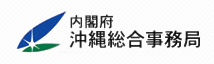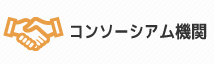【講義】5/1 第4回飲食ビジネス概論
2017.05.09
第4回 飲食ビジネス概論 担当:上地恵龍
第4回は、「地域経済活性化に貢献する移動食」ということで、駅弁についてとりあげました。
まず「弁当」という文化が、近年海外でも人気になっており、アメリカ、フランスでのニュースを見ました。弁当はそのまま「BENTO」という単語になっており、本屋には弁当の料理本が売られていたり、弁当箱のコーナーもあるほど人気があるようです。
さて、駅弁ですが、学生に食べたことがあるか質問をしたところ、県外出身の学生は「食べたことがある」でしたが、沖縄出身の学生となるとほぼほぼおらず、内地に旅行に行ったときに食べたことがあるという学生が1名いただけでした。
そもそも、駅弁は、「駅」で売っている「弁当」なので、車社会沖縄には馴染みがないのですね。内地出身の私は、子供の頃、お土産にもらう駅弁にワクワクしたものです。デパートで駅弁フェアがあると、その地へ行った気になってつい買ってしまう魅力が駅弁にはあると思います。
駅弁の歴史は、元々は鉄道建設の作業員のための食事が起源のようで、それが乗降客にも提供されるようになり、地域の食材を使うことで、地域のブランド力向上や、地産地消に貢献するようになったということでした。
また、日本の「鉄道大国」という面や、弁当を持ち歩くことに抵抗がない気質、各地に特産品があるという地理的優位性が結びついてできた、日本独特の食文化になったそうです。
とはいえ、時代と共に市場は縮小しており、常温保存の駅弁は消費期限が短く廃棄率がコンビニなどの倍の10%あり、そこには、規制があって消費期限が近くなったものを値引きできないなどの理由もあるようです。また、鉄道の高速化による乗車時間の短縮、駅構内に整備される「駅ナカ」店の増加、コンビニの存在、固定窓式で開閉できない車両の増加などの理由もあり、老舗業者が撤退するということもあるということでした。
そこで、イベント出店や保温式・加熱式駅弁の開発などにより、駅弁による地域活性化を図る取り組みが行われるようになり、デパートで行われた全国の駅弁が一同に会する「駅弁大会」に出店する店の密着取材の様子を見ました。上位に選出されることで、全国区になったものもあるほど影響力があるのだそうです。
近年では、「駅」だけでなく「空弁」「球弁」「速弁」「道の駅弁」などもあり、各地域で工夫を凝らした弁当が販売されているということでした。
文責:観光産業科学部 宜志富知恵子