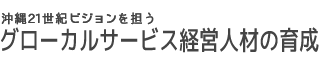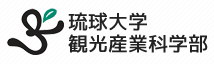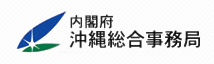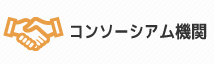【講義】5/16 第6回飲食ビジネス概論
2016.05.16
第6回 飲食ビジネス概論 担当:上地恵龍
外部講師:沖縄県飲食業生活衛生同業組合 理事長 鈴木洋一氏
第6回も先週に引き続き、沖縄県飲食業生活衛生同業組合 鈴木理事長が講師としてお見えになりました。
前回の復習がてら、沖縄の食文化はアメリカ支配と切り離せないというお話があり、タコス、ステーキ、ファストフード、居酒屋がどうやって発展してきたかについて説明がありました。
講義のテーマは「沖縄県飲食業界の取り巻く外部環境の変化」ということで、外食マーケットの現状についての講話がありました。
・国内での人口減少にともない、マーケットそのものも縮小する。ただし沖縄に限っていえば、人口は増え、観光客数の増加も助けになっている。
・飲食店のライバルは、同業者ではなく「コンビニ」
セブンイレブン1社の売上が、大手飲食業10社の合計売上よりもはるかに上回っているほど、コンビニが台頭している。
・従業員のパート、アルバイト率が8割と高い。
今後の予測として、正社員率が3割程度まで上がってくる。(人材育成が必要なため)、パート、アルバイトは外国人になっていく。
・原価と人件費が経費の半分以上を占めている。(だいたい65% 残りの35%で家賃、光熱費を賄う)
ということでした。
前回、今回の講義をうけ、宿題となっていた「琉球料理について考える」では、学生から、
・小さいうちから食べなれているようにすると継承されていく。たとえば、マクドナルドはおもちゃをつけて子供に買わせ、食べなれたものとして定着させている。
・沖縄にずっと住んでいるが、琉球料理についてあまり知らない。情報そのものが広まっていない。メディアを使って広めていくことがまずは必要。
・沖縄にずっと住んでいるが、家庭で食べるものしか知らない。琉球料理は親しみがない。小さいころから食べて、沖縄の人はこういうものを食べていると言えるようにしないといけない。
・外国人観光客にも県外からの観光客にも受け入れられるアレンジが必要。例えばフレンチとコラボなど。
・情報が少ない。琉球料理をどこで食べられるか聞かれても答えられない。県外、海外よりもまずは県内の人に改めて知ってもらう必要がある。県内の人に広まると民泊などでふるまうことができ、観光客にも広まっていくのではないか。
・ターゲットを観光客ではなくビジネス客にする。観光客には高額な琉球料理はハードルが高い。MICE施設建設もありビジネスでの来沖が増えること、ビジネス客は会社経費なので多少高額でも出すことなどから、ビジネス客をターゲットにしていくといいのではないか。
という意見がでました。
そもそも、「琉球料理」と「沖縄料理」の違いも曖昧で、和食と琉球料理も違うジャンルであるのに一緒くたになっていることもある。
外資系のホテルは、県内にあっても、琉球料理のレストランが入っていない。「琉球料理」は仕込みに時間がかかるので携わる人が減っているが、失ってから大切さに気付くのでは遅いというお話がありました。

講義後に全員で集合写真

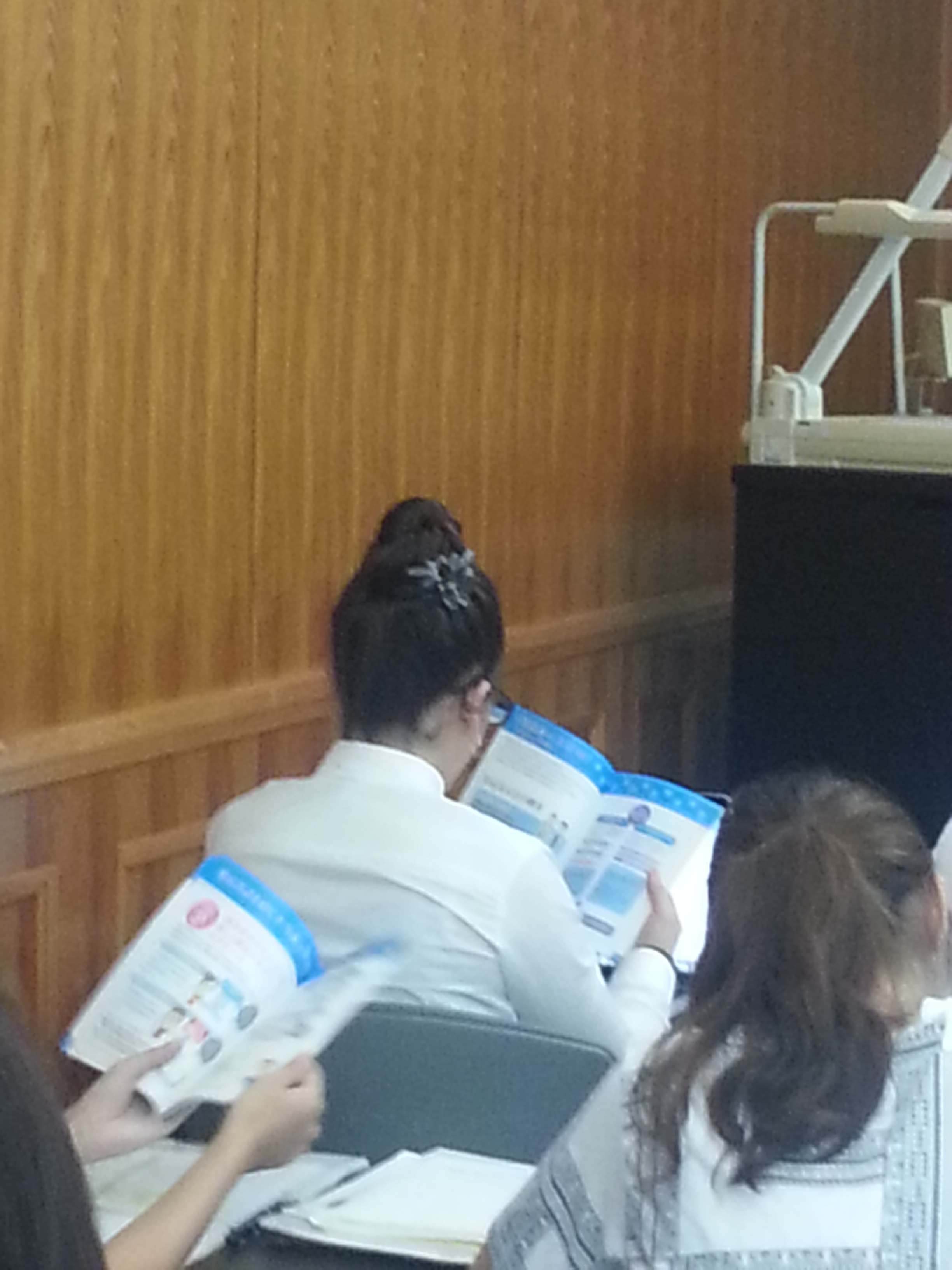
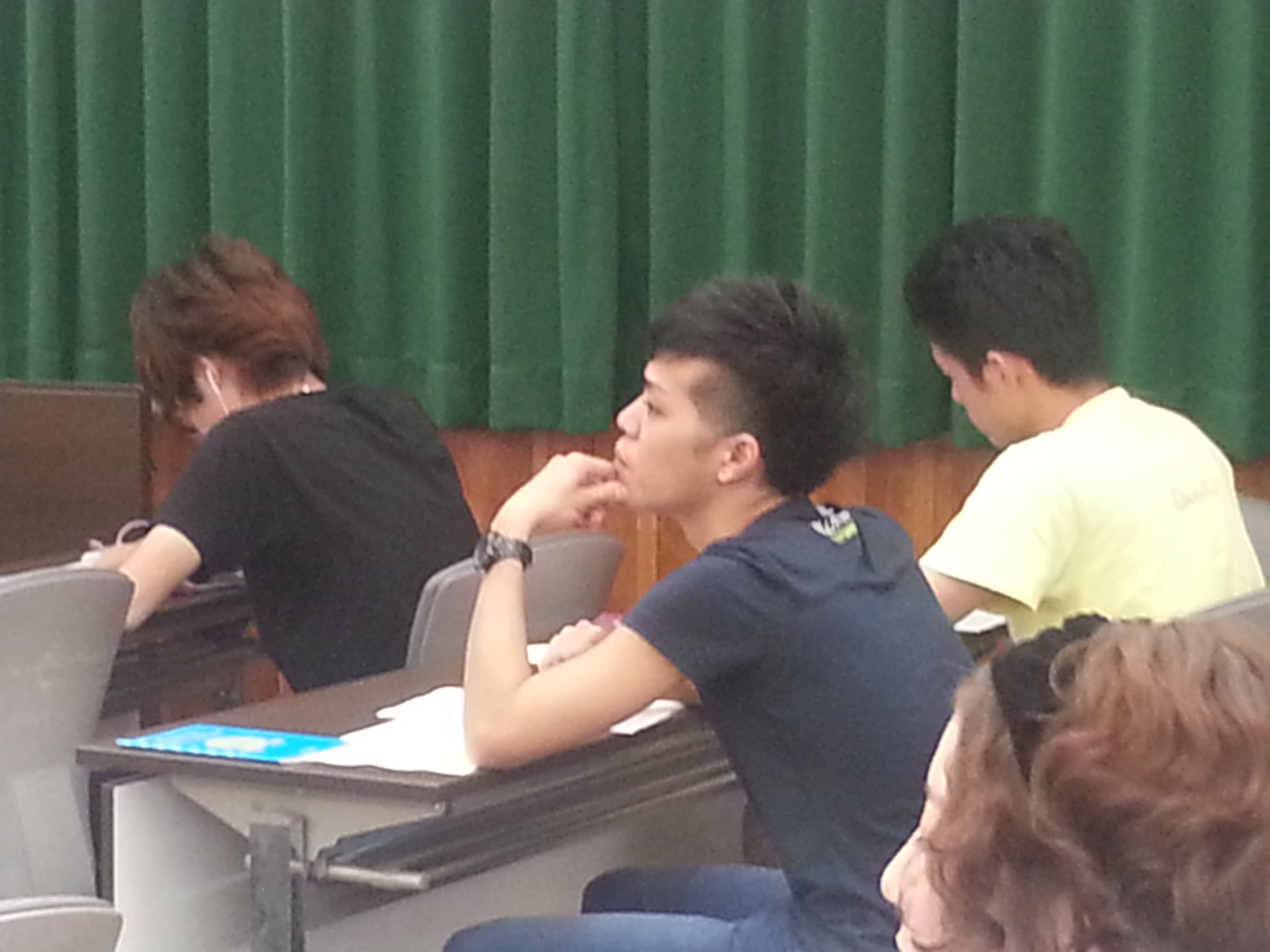


文責:地域連携推進課 宜志富知恵子